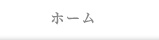通勤手当は、消費税の仕入税額控除の対象となるか(マイカー通勤編)
名古屋の税理士 南雲和江です。
きょうは、給与の支給の際に一緒に支払われる通勤手当が、消費税の計算上、仕入税額控除の対象になるかどうかについてお話したいと思います。
役員や従業員に給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税が課税されないこととなっています。
平成26年3月31日現在、マイカーなどで通勤している人に支給される手当が非課税となる限度額(所得税が課税されない金額)は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
※(通勤距離⇒直線距離)と思いがちですが (通勤距離⇒通勤経路に沿った長さ)で測ります。
平成26年3月31日現在
|
片道の通勤距離 |
1か月当たりの限度額 |
|
2キロメートル未満 |
(全額課税) |
|
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
|
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
6,500円 |
|
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
11,300円 |
|
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
16,100円 |
|
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
20,900円 |
|
45キロメートル以上 |
24,500円 |
たとえば、自動車通勤の従業員に燃料費負担分として 1㎞当たり16円支払うことにしている法人があるとしましょう。
1か月の労働日数22日で、会社と自宅との距離が片道で10㎞だったとすると
16円×(10㎞×2(往復))×22日=7,040円の支給
上記の表で見ると 片道10㎞の所得税の非課税限度額は6,500円ですから
超過している7,040円-6,500円=540円は、所得税が課税されることになります。
では、消費税ではどうでしょうか・・・・
消費税法では、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」は仕入税額控除対象となるとされています。
最近では、燃費が非常に優秀で1ℓ当たり30㎞も走るというフレコミの自動車も売られているようですが、そういう自動車は、稀でしょう。
私の感覚では、1ℓ当たり10㎞~13㎞ 走行できる自動車が一般的じゃないかと思います。
また、最近のレギュラーガソリンの1ℓ当たりの金額も高騰していますし、場合によっては、通行料を払わなければ通行できない道路さえあります。
こうした実状を考慮すれば、所得税法の非課税限度額を超えている部分の金額であっても、その者の通勤に係る距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的である通勤経路によって計算されていれば、消費税は、仕入税額控除の対象となると考えます。
消費税法基本通達11-2-2《通勤手当》
所得税法9条、所得税法施行令20の2
➡ 注意 平成26年10月において非課税限度額の改正がありました。
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
詳細は、平成26年(2014年)11月5日のNAGUMO通信をご覧ください。